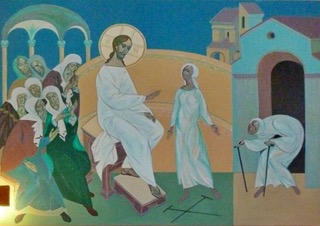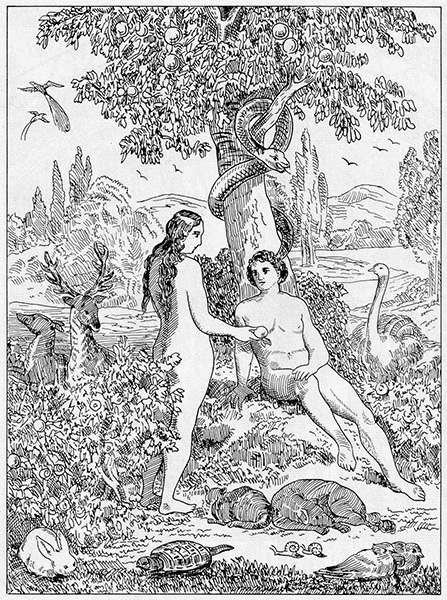わたしは言っておく。
悪人に手向かってはならない。
だれかがあなたの右の頬を打つなら、
左の頬をも向けなさい。
(新約聖書「マトフェイ(マタイ)福音書」5:39)
あなたの頬を打つ者には、
もう一方の頬をも向けなさい。
(新約聖書「ルカ福音書」6:29)
この福音を読み、いつも思います。
人を暴力的に殴ったり、打つ手があるのだ、と。
ときには言葉の暴力もあります。
うわさ話、陰口ばかりでなく、最近ではパソコン、スマホの普及などによりインターネット通信を利用した、悪意ある中傷、根拠のない誹謗(ひぼう)などが広がっています。
自らには何の汚点、加害のないにもかかわらず、一方的に打たれ炎上させられつづけるのは、すごくつらく、悲しいものです。
たとえば一人の人間が、左手でひとを打ち、右手でひとを祝福しているとしたら、どうなのでしょう。
面従腹背の背信者、ひとりの人間の矛盾は、けっきょく人を、自分を滅ぼす源になります。格言には、こうあります。
二心(ふたごころ)ある者の言葉は蜂蜜、その行動は槍である。
神と悪魔とに、同時に仕えることはできない。
神父がたびたび、両手を天にさし上げて祈る姿勢には、神を呼び求めるこころが満ちています。
悪を求めるのではなく、神を求めます。
二心なく、神ひとりを求めます。
そのため、両手を天にさし上げて祈ります。
正教会には、人への祝福をする手の甲に接吻するという慣習があります。
主教品や神父(司祭)が祝福する右の手を、信徒は両手のひらを重ね、恭(うやうや)しく、優しく接吻するのです。
かたほうの手で人を祝福し、もうかたほうの手で、人を殴ったり打ったりする、そういうことを信仰者はしません。
神のこころを受けとめ、その愛の温もりを感じ、両手で包みこみます。
祝福をうける手があり、さらに別に人へ祝福を恵み伝える手があります。
愛を創造し育てる手があり、信と希望を伝える手があります。
正教会の聖堂、祈りでは、神父がこう祈って手をかかげ、十字を画きながら祝福します。
「衆人に平安」
わたしたちは聖神(せいしん)の恩寵(おんちょう)を両手いっぱい受けとめるため、こころよりの笑顔、豊かな気持ちで応えましょう。
そのとき、天使がふたつの翼をたたむがごとく、わたしたちは胸の前で両手を組み、頭(こうべ)を垂れ、祝福を受けとめましょう。
「なんじの神(しん)にも」と。
(長司祭 パウェル 及川 信)